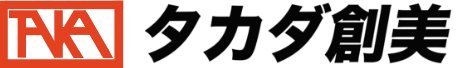NEWS & COLUMN
お知らせ&コラム
-
2025.01.27
コラム
ビニールカーテンのばたつきを解決!強風対策の設備5選
ビニールカーテンは、工場や倉庫、作業現場での効率的な間仕切りとして大変便利な設備です。しかし、強風が吹き込む現場では、「カーテンがばたつく」という思わぬ問題が発生することも。 些細な問題に聞こえるかもしれませんが、まともに開閉がこれらの課題は設備選定時に見落とされがちですが、後になって大きな問題となるケースも少なくありません。 特に初めて設備を導入する方や、現在の環境改善を検討している方は、事前に対策をよく調べておくことが重要です。適切な対策を選ぶことで、カーテンの耐久性向上やコスト削減だけでなく、快適な作業環境の実現につながります。この記事では、ビニールカーテンのばたつき問題を解消するための設備をご紹介!事前に知っておくべきポイントと検討するべき設備を解説しますので、導入前の参考にぜひご活用ください。 設備導入前に知っておくべきポイント ビニールカーテンを導入する際、現場の環境を正確に把握し、適切な設備を選ぶことが成功のカギです。 業者のサポートはもちろん重要ですが、現場環境を最もよく知るのはあなた自身。業者とのやり取りをスムーズに進め、最適な提案を受けるためには、事前に知っておくべきポイントを押さえることが大切です。 ここでは、トラブルを未然に防ぎ、満足度の高い設備導入を実現するための2つの重要なポイントをご紹介します。 1. 現場の風環境を把握する 風の影響を正確に見極めることが、ばたつき防止の第一歩です。 現場の風環境を理解することで、業者に対して具体的な要望を伝えやすくなります。以下の3つの視点を事前に確認しておきましょう。 風の入り口や抜け道をチェック 工場や倉庫のレイアウトによって、風が吹き込む方向や強さは大きく異なります。たとえば、作業エリアの広さ、風が抜けやすい動線などを確認してください。特に、風が集中して吹き込むエリアでは、強風に耐えられる設備が必要になります。 開口部の大きさを確認 開口部が大きければ大きいほど、カーテンのばたつきは大きくなります。 たとえば、大型倉庫の出入り口や、トラックが通る大開口スペースでは、安定性の高いカーテンが必須です。 季節風を考慮する 冬場に特定の方向から強風が吹く地域では、特に意識する必要があります。過去の経験から把握しておくと適切な選定がしやすくなります。 2. 開閉頻度と作業性を考える 高頻度で開閉が必要な現場では、開け閉めの力が少ない設備の方がよいかもしれません。 開閉が少ない場合は、強度の高いスライドカーテンや、半固定にできるグランドフックなども検討の余地があります。 ビニールカーテンのばたつき防止対策 ビニールカーテンが強風によってばたつくのを防ぐには、環境や用途に応じた設備選定が重要です。以下に、現場の条件に適したばたつき防止のための具体的な方法を6つご紹介します。 (1) タッセルで固定する方法 カーテンを側面からタッセルで巻くことで、カーテンをオープンにした状態のばたつきを抑えることができます。既に設営済のカーテンでも簡単に取り付けられます。 (2) ウェイトチェーンの利用 カーテンの裾にウェイトチェーンを取り付けることで、風による動きを抑えます。チェーンの重さを調整することで、カーテンの安定性を高めることが可能です。 (3) グランドフックの利用 頻繁に開閉しないカーテンには、地面に取り付けたフックを使用し、カラビナなどでしっかり固定する方法が有効です。この方法により、強風時のカーテンの動きを最小限に抑え、安定性を向上させることができます。 (4) 芯材カーテンの導入 カーテンに芯材を入れることで、剛性が増し、安定性が格段に向上します。また、落としピンを併用することで、カーテンを閉じた状態で風に煽られにくくすることができます。この方法は、耐久性を求める現場に最適です。 (5) スライドカーテンの導入 ジャバラ状のスライドカーテンは、芯材にXバーを追加することで剛性を高め、強風でも形状を保ちやすくなります。特に大型カーテンでその効果を発揮し、さらにボルトローラーを採用することで開閉操作もスムーズに行えます。 ビニールカーテンのばたつき防止が必要な理由 騒音の軽減 ビニールカーテンがばたつくと、強風のたびに大きな音が発生し、作業環境の騒音レベルが上昇します。この騒音は作業員にとってストレスとなり、集中力の低下や業務効率の悪化を招く原因となります。ばたつきを防止することで、静かで快適な作業環境を維持でき、作業員の満足度とパフォーマンスの向上につながります。 カーテンの耐久性向上 強風によるばたつきは、カーテンの素材に余計な負荷をかけ、摩耗や損傷を引き起こします。この状態が続くと、破れや裂け目が生じやすくなり、修理や交換の頻度が増加します。ばたつき防止対策を行うことで、カーテンの寿命を延ばし、維持管理にかかるコストを削減できます。特に、耐久性を求める現場では不可欠な対策です。 ビニールカーテン以外の手段 強風対策として、そもそもビニールカーテンを採用しないという選択肢も検討できます。ビニールカーテンは透過性が高く、採光性や視認性に優れていることが大きなメリットですが、現場の状況によっては他の手段が適している場合もあります。以下に、ビニールカーテンに代わる代表的な方法をご紹介します。 ・メッシュ生地を採用する 強風が通り抜ける「メッシュ生地」を用いることで、風圧を大幅に軽減することができます。完全に密閉することはできませんが、意外にも雨風をある程度防ぐことが可能です。また、通気性を確保しながら作業環境を快適に保つため、特に風通しを必要とする現場で有効です。 ・引戸の設置 ビニールカーテンに比べると、引戸は形状の自由度が制限されますが、その分耐久性や安定性に優れています。強風の影響をほとんど受けず、開閉の際も力を要しないため、頻繁に使用する開口部には最適です。また、引戸はしっかりと固定できるため、防音や防塵効果も高まります。 ビニールカーテンは周囲の環境と設備選択が重要 ビニールカーテンの設置は、周囲の環境や用途に合わせた設備選択が成功のカギです。特に強風によるばたつきは、作業効率や快適性を損なうだけでなく、長期的なコストにも影響を与えます。適切な対策を講じることで、カーテンの耐久性を向上させ、静かで快適な作業環境を維持することが可能です。 また、場合によってはビニールカーテン以外の選択肢を検討することも、最適な解決策につながるかもしれません。周囲の風環境や開閉頻度をしっかりと把握し、自社の現場に最も適した設備を選ぶことが重要です。 タカダ創美では、長年の経験と豊富な実績をもとに、お客様の現場環境に最適なソリューションをご提案しています。現場の状況に応じたカスタマイズや、具体的な問題解決のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 -
2023.11.06
コラム
防寒に役立つビニール間仕切り・ビニールカーテンの選び方(工場編)
比較的温かい2023年ですが、それでも冬はやってきます。人手不足が申告となり、働く環境が重視されている昨今。人手がどうしても必要な製造業の工場では人が集まらずに倒産というニュースも目にします。選ばれる職場とするためにも、ビニール間仕切り・ビニールカーテンを使った防寒対策を検討されてはどうでしょうか。その際に役立つ情報を4つにまとめみました。 1.きたるべき冬に備えて、ビニール間仕切の効果は? ビニール間仕切りは主に冷気や風の遮断に優れています。熱貫流率はそれほど高い性能は有していませんが、とにかく暖かな空気を外に逃さない、逆に冷たい空気を中に入れないことがビニール間仕切りの大きな効用であり、メリットです。大きな工場では人がいるスペースといないスペースが往々にして分かれています。人がいるスペースには暖かな空気を閉じ込め快適に、それ以外は余計なエネルギーをかけないというメリハリをつけることで、冬場の暖房効果を高め省エネに貢献できます。特に電気代、灯油代ともに高騰している現状ではその効果は月に数万円では聞かないケースも有るほどです。 2.どんな素材を選ぶべきですか? ビニール間仕切りに使用できる素材は様々なものがありますが、ほぼ80%以上の確率で選択されるのが、糸入り透明ビニールの厚みが0.3mmのもので、防炎と静電気防止の性能がついたものとなります。なぜこのシートが選ばれているのか、端的に言えば、コストパフォーマンスに優れているからにほかなりません。視認性に優れ、糸が入っているため寸法安定性、少しの破れでは破れ広がらない耐久性、厚みが薄いぶん柔らかく、それでいて空気の遮断は問題ありません。ですので、特別な理由がない場合はこちらのシートを使うこととなります。もしとても寒い場所に設置するのであれば、耐寒性の素材もありますが、それよりもどちらかといえば、縮を考慮して少し大きめのカーテンしたほうが安心かもしれません。(注意、ビニールは寒さで縮むというよりは、畳んだ際の折り目が伸びずに幅が狭まります。つまり暖かくなれば、自然とカーテンが短くなったような錯覚は解消します) 3.糸入り透明ビニールt0.3防炎静電がつかえない特殊な環境って? 一般的に一番多いパターンは、不燃性能を求められた場合です。法令により不燃素材を使わなければならない場合は、防炎性能だけではもちろん不十分です。防虫効果を高めたいときにはイエローやグリーンの素材を使うこともありますが、間仕切りをするだけである程度の効果は得られるためマストではありません。他にマストとなるのが例えば、高温環境でに設置する場合です。ビニールはプラスチックですので、通常60度程度から変形が始まります。そのため、そういった環境では耐熱性の素材を選ぶ必要があります。 4.どんな形状、どの場所を優先するべき? 一番最初に抑えるべきなのは外部へとつながる開口です。シートシャッターなどの開閉速度の早い出入り口であれば問題ありませんが、重量シャッターや動きの遅い電動シャッターの場合開けっ放しのことも少なくありません。そういった場所にこそ開けしめの簡単なビニールカーテンや、手を使うのが煩わしいのであればのレンシートを取り付けると冷たい空気が内部に入らず環境改善が履かれます。次に考えるべきは人がいる箇所を重点的に囲うことです。ビニールブースにすることが一番手っ取り早く、エアコン設置もすることで理想的な環境が整います。そこまでしなくとも、衝立をつけるだけでも、時々開口を開けた際に吹き込む風を遮断できそれまでとは違った環境となります。また、よくご相談を受けるのが、中二階や、階段です。せっかく暖かな二階で仕事をしているのに、そこから冷気が入ったのでは意味がありません。全室や荷揚げの開口には開閉式のビニールを設置することで暖かさが段違いになります。 5.まとめ ビニール素材は他の健在に比べ、短期間、低コストで働く環境改善が図れる有効な方策です。今回は糸入り透明ビニールを特にプッシュしていますが、弊社では屋外で使われるテント倉庫の生地を屋内でも使っている場所があります。視認性は悪くなりますが、壁としての利用であれば強度もビニールとは段違いにあり、現在15年以上使われておりますが、ベタつきもくすみもさほど気になりません。工場によってはオイルミストが飛んでいたり、天井クレーンをどうしても使わなければならない環境もある可と思います。ただ、働く環境改善は待ったなしに求められていますので、ぜひ一度お気軽にご相談にただければ幸いです。 ビニール間仕切りについてより詳しい情報はこちらから! ビニールカーテンについてより詳しい情報はこちらから! ビニール製品の施工事例はこちらから! -
2021.06.14
コラム
工業用の塗装ブースの紹介
今回はときおりお問い合わせを頂く工業用の塗装ブースを紹介します。生地のしなやかさを生かした製品ですので、ぜひご一考ください。 通常、自動車を塗装するような大型塗装ブースは、ゴミやホコリをほぼ完全にシャットアウトし、風の流れをコントロールすることでインクの舞い上がりを防ぐなど、とても高性能です。そのようなブースは綺麗な塗装を行うには欠かせませんが、そのぶん高価でスペースを占有します。 弊社が提供する塗装ブースは、素材に生地を用いています。使用しないときはジャバラのように収納してスペースを有効活用でき、掃除も簡単。換気扇を設置することで乾燥もできます。塗料の飛散を防ぐのが目的であれば、カーテンの設営だけでも十分な場合もございます。 求められる品質次第で、選択肢の1つとしてお考え頂けるかと思います。導入実績も多数ありますので、ご興味があればぜひお問い合わせください。 施工事例 電動スライド塗装ブース 開口を大きくすることで、大型の製品を持ち込み塗装することができます。電動化しているのでボタン1つで伸縮できます。壁面に換気ダクトも備えています。 乾燥ブース 換気ダクトを設けた乾燥ブースです。透明な生地を利用しているので、展開して内部で作業を行うときも光量を確保できます。 間仕切りカーテンによる塗装スペース 簡易的でよければ、間仕切りカーテンを利用する方法もございます。吊り棒を使用し天井からレールを吊り下げているため、カーテンの位置も自由に設営することができます。 間仕切りカーテン・壁による塗装スペース 塗料や臭気の飛散防止が目的であれば、カーテン・間仕切り壁の施工で十分な場合もございます。 -
2020.11.02
コラム
ビニールブースの省エネ効果について
工場内にビニール間仕切りやビニールブースを設置する目的の一つが空調機器の効率化による省エネ効果かと思います。しかし実際にどの程度費用を削減できるか計算するのはなかなく難しく、導入に二の足を踏む方もいらっしゃるのではないのでしょうか。確かに正確に効果を計算するには高度なシミュレーションが必要になりますが、概算であれば簡単に計算ができます。 そこで今回は状況を簡略化し、実際にどのくらいの費用削減効果があるのかをざっくりと試算してみたいと思います。概算ですので、あくまで参考に留めてください。 おおよそ費用削減効果の計算 例えば、工場サイズ幅10m 奥行き10m 高さ4mがあり、 1/4のビニールブース幅5m 奥行き5m 高さ2mを設置し 内部に空調を配置する場合を考えてみます。 15畳(23.25㎡)目安のエアコンを設置する場合(一台あたり¥150,000とします)、 ビニールブースは1台の設置となり、工場全体の場合は8台となります。 工場全体については、高さが2倍となりますので、この数量となります。 ブースの価格を参考として、ブースの表面積あたり1万円/㎡とすると 下記のような初期投資となります。 工場全体を空調した場合 エアコン8台✕¥150,000=¥1,200,000 ブースを空調した場合 エアコン1台✕¥150,000+表面積75㎡✕¥10,000=¥850,000 となります。 工場全体を空調できるため、エアコン8台設置したほうが良いような気もしますが この規格のエアコン1台の年間電気料金は¥45,000ですので、そちらを加味すると 下記のような計算結果となります。 工場全体を空調した場合 初期投資¥1,200,000+ランニングコスト10年¥3,600,000=¥4,800,000 ブースを空調した場合 初期投資¥850,000+ランニングコスト10年¥450,000=¥1,300,000 となります。 まとめ 極端な概算ですが、さらに、三角屋根の分の体積や、天井からの入熱、空調を行き渡らせる風の流れ等を考慮すると工場全体に空調を行き渡らせることがいかに困難かおわかりいただけるかと思います。(エアコン選びでかなり変わってくると思いますので、注意してください!) ビニールブースの場合、エリアが制限される大きな欠点がありますが、区分けをすることで防塵、防虫効果も期待できます。それらを加味するとビニールブースはそれほど損のない選択かと思います。 →ビニールブースのページはこちらから← -
2020.09.30
コラム
工場のゾーニングについて
2020年6月にHACCP(ハサップ)が義務化され、食品を扱う事業者には衛生管理の厳格化が求められるようになりました。この義務化に伴い、多くの事業者が「ゾーニング」を含む一般的衛生管理プログラムの整備を進めています。 しかし、ゾーニングは食品業界だけに限らず、鉄工所や化学工場などのものづくり現場でも品質向上のために必要な施策でもあります。 ゾーニングの方法はさまざまですが、特にビニールカーテンはコストパフォーマンスに優れたバランスのよい設備の1つです。 本記事ではゾーニングの基本と、ビニールカーテンを活用した事例についてご紹介します。 ゾーニングとは ゾーニングとは、作業区域を明確に区別し、異物の侵入や汚染を防ぐ仕組みです。例えば、工場の衛生区域と汚染区域を分け、人や物の動線を管理することで、製品の品質を守ります。 日本では、玄関で靴を脱ぎ家の中の清潔を保つ習慣があります。これと同じように、工場内でも適切な仕切りや管理が重要です。 工場におけるゾーニングの基準 では、どのような基準でゾーニングを行うべきなのでしょうか? 工場でゾーニングを行う際、一般的には「製造工程による区分」か「衛生度による区分」、どちらかの基準が用いられます。 製造工程による区分 製造工程で区域を分けた場合、衛生管理の面だけでなく、製品が他のラインに混入するなど製造面での失敗を防ぐことができます。しかし、2つの問題を一度に解決しようとすると観点がブレてしまい、本来の目的を失った中途半端な改善になってしまうことがあります。異物の侵入を防ぐことが目的ならば、まずは衛生度に観点を絞ってゾーニングを考えることをお勧めします。 衛生度による区分 ゾーニングは衛生度によって段階を設けるのが理想的です。段階は、[清潔区域・汚染区域]の2段階、もしくは[清潔区域・準清潔区域・汚染区域]の3段階がよく用いられます。工場の規模や必要な衛生度に応じて、何段階でゾーニングを行うか考えましょう。人や物の動線は段階を跨ぐことのないように計画しなくてはなりません。 ゾーニングの手段と比較 ゾーニングを実現する手段は多岐にわたります。それぞれの特徴がまとめられている表を引用しました。 table#taktable > tbody > tr > td {border:1px solid green;width:90px; } table#taktable > tbody > tr > td:first-child {width:200px; } table#taktable > tbody > tr:nth-of-type(even) {background:#F0F0F0; } 名称 仕切効果 見通し 変更の容易さ コスト ハード隔壁 ◎ △ × 高 スライドドア ◎ △ × 高 スイングドア ○ ◎ △ 高 ビニールカーテン ○ ◎ ○ 中 衝立 △ ◎ ◎ 低 チェーン △ ◎ ◎ 低 ライン △ ◎ ◎ 低 なし △ ◎ ◎ 低 引用元リンク 中でもビニールカーテンは、バランスのよい選択肢となっています。 清潔な区域に埃や虫の侵入を防ぎたい場合、まずはビニールカーテンの導入を検討するとコストを抑えられるかもしれません。 ビニール製品でゾーニングを強化 弊社ではビニールカーテンやビニールブースなど、ゾーニングに最適なビニール製品を提供しています。 お客様の工場を採寸し、工場レイアウトや設備に合わせた形状を提案します。 ビニールカーテン 取り付けが簡単なビニールカーテンは、清潔区域と汚染区域の出入り口に最適です。 防虫生地や透明タイプなど、用途に合わせて選べます。 特に手を使わずに通過できるノレン状のカーテンは、作業効率を損なうことなく防塵・防虫を実現します。往来の多い場所におすすめです。 👉ビニールカーテンの詳細はこちら ビニール間仕切り カーテンだけではなく、ビニール壁やアルミドア、シートシャッターなどと組み合わせることで、 広い工場を効果的にゾーニングすることができます。清潔区域への前室としても活用できます。 👉ビニール間仕切りの詳細はこちらから ビニールブース ビニールブースは工場内に密閉された空間を設けます。埃や虫の侵入を防ぐだけでなく、空調機を別途設置することで快適に作業できます。 👉ビニールブースの詳細はこちらから ベルトコンベアの事例 ベルトコンベアの出入り口をビニール製品で区切った事例です。 ゾーニングとコンベアの稼働を両立しながら、防塵・防虫対策が可能です。 👉この事例の詳細はこちらから ビニールカーテンの事例 ビニールカーテンで間仕切りした事例です。箱詰め後など出荷前になる製品の一時的な保管場所ならば、ビニールカーテンで十分な場合もあります。 👉この事例の詳細はこちらから ゾーニングで工場の衛生環境を改善しよう 衛生管理や品質向上のために、ゾーニングは欠かせない取り組みです。弊社のビニール製品を活用すれば、低コストで柔軟なゾーニングを実現できます。ぜひ、お客様の工場に合わせた最適なソリューションをご提案させてください。 お問い合わせは👉こちら👈からお気軽にどうぞ! -
2020.07.28
コラム
屋内間仕切りの不燃ビニールの選び方
ここ数年、屋内のビニール間仕切りをする際に、防炎ではなく、不燃を要求されることが 増えてきました。理由としては、危険物を取り扱う場所であったり、引火しやすい場所であったりと 不燃材の使用が義務付けられており、消防署の方から指導が行われている場合が主です。 もともと屋外では基布がガラス繊維で織られたテント生地がありましたが、 近年では屋内間仕切り用のシートも数社から発売されております。 その中でよくご質問を頂くのが、不燃に透明材はあるかどうかです。 もともと内部を明るく保ちながら、圧迫感なく仕切られることがメリットですので とても気になるところかと思います。結論から言えば、透明の不燃材料はあります。 しかし、不透明(有色)の不燃材と比較すると7倍以上の値段差があるため、 必要なところをよく検討しなければなりません。 例えば、採光性、視認性すべてを透明にできれば良いですが、 現実的にはコストが掛かりすぎます。そこで、弊社では天井には少しでも 内部が明るくなるよう白色系のシートをおすすめしております。 白系にするだけでもかなり内部は明るくなります。 また、視認性については、側面の目線部分に透明材料を、その他の部分には 不透明材料をおすすめしております。 不燃材料のシートはほとんどが1m幅の巻物ですので、1m幅か、50cm幅の 透明固定部分をいれることで、内部の様子を十分に把握することができます。 防炎材料は不燃材料と比べ、高価な材料となりますので、 できること、できないことをテント屋と検討をしながら 使用を決定していくことが大切かと思います。 ビニールカーテンにはできるの?不燃ビニールにはどんな種類があるの?という よくある質問については別のコラムで説明したいと思います。 もし気になる方はお気軽にお問い合わせください。 半透明不燃間仕切り 透明不燃材間仕切り 目線高さ一部透明不燃間仕切り -
2020.06.23
コラム
間仕切りによる工場の騒音対策
日々、工場では機械音が鳴り響いていることかと思います。この騒音が近隣住民に迷惑にならないか、気にかけけている方は多いのではないのでしょうか。 一方で軽視されているのが、従業員への負担です。コミュニケーションで大声を出すことが必要になる環境では、作業効率の低下や事故の発見が遅くなるなどの悪影響が考えられます。更にはストレスによる疲れや難聴など、健康を害する事態にも発展しかねません。近隣住民への配慮だけでなく作業員の効率や健康も考慮すると、騒音は無視できない問題です。 今回は従業員のための騒音対策としていくつかの設備をご紹介し、最後に弊社としてどのような解決方法を提案できるか紹介します。 防音材によるカバー 騒音の対象となる機械を防音カバーで覆います。遮音効果が非常に高く、従業員のストレスも大幅に軽減されます。まずはここから検討したいところです。コンプレッサーやポンプなど操作が必要ない・時々しか触らない、メンテナンスの頻度の低い設備ならば問題なく導入できると思われます。 機械の形状が複雑で大型な場合は、綿密な設計が必要なためそれなりのコストがかかります。またオペレータの直接操作が必要になるような機械の場合はカバーが難しこともあるので、そのような場合は防音ルームやその他簡易的な方法を検討する必要があります。 防音材による隔離ルーム(防音ルーム) 機械と作業員のスペースを防音室として覆ってしまう方法です。防音室内にいる作業員には負担を強いることになりますが、高い効果を発揮します。 問題は防音壁が半固定になってしまうことです。既存の動線を邪魔しないようレイアウトを策定し、スペースをしっかり確保した上で設営しなければなりません。また、複雑な工場レイアウトに対応しづらいのも問題です。機械や配管などを考慮すると、それなりのコストが必要になります。 防音材によるパーテーション 一般的にオフィスや個別塾で見られるパーテーションですが、騒音対策として工場内に設置するタイプがあります。吸音効果を持つものであれば機械の高い音を抑えられ、遮音性を持ったものであれば外に音が漏れづらくなります。できるだけ既存の壁と併用して、騒音源を囲い込むように設営するとよいでしょう。騒音源が移動する、対策範囲が広い、機械の都合上覆うのが難しい場合に有効です。移動タイプのパーテーションを利用する方法もあります。 ただし、音は障害物等をまわりこんで伝わる回折という特性があり、少しの隙間でもそこから音が漏れてしまいます。配管や機材が邪魔してしまうような環境では、大きな効果は期待できないでしょう。また、移動タイプのパーテーションでも動線を邪魔してしまうことになります。防音ルームほどでないにせよ、しっかりとした計画が必要になります。 生地を用いた間仕切り 弊社では、ビニールブースやビニールカーテンなど、生地を用いた間仕切りによる騒音対策を提案しています。 大きなメリットは、既存の工場をそのまま活用できる自由な設計が可能なことです。生地の軽量さを活かして複雑な工場レイアウトにも容易に対応でき、カーテンを利用すれば現状の動線を維持したまま出入り口を設けることができます。配管や上述の設営が難しい場合にご検討してみてはいかがでしょうか。 もちろん、生地は壁やパーテーションなどに比べて厚さが薄くて薄いため、上記の特化した製品ほどの大きな効果は望めません。しかし、現在は生地に防音用の素材を織り込んだ効果の高い生地がメーカーから発売されており、高い防音効果を発揮しております。 また、防音効果は低下してしまいますが、弊社が普段提供している安価なビニール間仕切りでも、2重に施工すればそれなりの効果(コンプレッサー・エアーバキュームといった音:約60db→50db)を発揮しています。ビニール間仕切りのメリットは、生地が透明なので室内が目視できることです。作業オペレータの様子が見えるので、事故が発生したときもすぐに気づくことができます。 施工前 施工後 弊社の間仕切りについては、下記に詳しく書いております。ぜひご覧ください。 https://www.takadasoubi.com/products/vinlymajikiri/ -
2020.06.22
コラム
工場・倉庫の荷捌きを改善しよう
品質管理や従業員の作業環境により一層の配慮が求められている昨今、管理者の方々は様々な改善方法を模索しているかと思われます。改善というと作業スペースに目が向きがちですが、改善領域はトラックの荷下ろしから既に始まっていると言ってもよいのではないのでしょうか。 弊社では、工場・倉庫の改善に貢献する製品を多く提供しております。今回は、テント製品でできる、荷捌き・搬入・搬出口の改善方法をご紹介します。 悪天候時の搬入・搬出対策 悪天候時の荷下ろしは、製品の品質や作業効率に悪影響を及ぼします。雨に濡れないよう急ぐあまり丁寧に作業できず、荷物を傷つけてしまうリスクが高くなります。また、雨に濡れた荷物の処理は当然、無駄な作業時間になってしまいます。スタッフの健康も心配です。スタッフが安心して作業できる環境は、作業効率の改善にも貢献します。 悪天候時も安心して作業できる環境づくりが重要になります。 荷捌きテント 上屋テントを工場・倉庫の搬入口に設けることで、悪天候時も荷捌きできるスペースを確保します。テント生地の軽量さを活かすことで高強度ながらも間柱の数を抑えられ、広い作業スペースと侵入経路を確保することができます。高さのある荷捌きテントなら、大型ウィング車もそのまま入れて作業が行えます。 大型庇 スペースが足りず荷捌きテントの設置が難しい場合は、せめて荷物を濡らさないよう庇(ひさし)の設置を検討してはいかがでしょうか。トラックのリヤドアを雨から守るだけでも、荷捌きに余裕ができ、事故を防止できます。 屋外カーテン 荷捌きの改善には余裕のあるスペースが必要不可欠ですが、そもそものスペース確保が難しい場合もあるかと思います。 荷捌き場を雨風から守るカーテンを設けることで、屋内環境に近づけることができ、一時的な保管スペースとして利用することができます。屋外にカーテンというと強度が心配な方もいらっしゃるかと思いますが、設置環境に合わせて適切な種類のカーテンを選択することで、台風にも備えることができます。 https://www.takadasoubi.com/news-column/p2087/ 搬入口の防塵・防虫対策 人やフォークリフトなどが頻繁に出入りする環境では、出入り口を常時開放している企業様も多いことでしょう。致し方ないことではありますが、砂ぼこりや虫の侵入ルートとなってしまい、空調を利用している環境では効率が低下して経費を圧迫することになります。弊社ではこの状況を改善する製品を提供しています。 シートシャッター センサーにより自動で開閉を行うことができるシートシャッターになります。特筆すべきはその開閉スピードで、シャッターの素材に軽量な生地を利用することで素早く開閉することができ、作業効率の低下を最小限に屋内環境を整えることができます。 ノレンカーテン 完全に入り口をふさがないため、作業効率を落とさずに屋内環境を改善することができます。ビニール生地を利用しており奥側を視認できるため、衝突事故を防止でき安全です。防虫仕様の生地を選ぶことで、光が漏れていても虫を寄せ付けません。競合製品としてエアカーテンがあります。効果としてはほぼ同様です。騒音や経費の面ではノレンカーテンが有利になりますので、比較の上ご検討ください。 -
2020.06.03
コラム
シャッターとカーテンで工場の防虫対策!役立つ設備紹介
工業製品の品質向上や異物混入防止の観点から、防虫対策は多くの管理者が直面する課題のひとつです。 特に夏から秋にかけて、どこからともなく侵入する虫に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。 今回は、虫の侵入を防ぐための効果的な設備と、その導入メリットについて詳しくご紹介します。 ぜひ、貴社の工場環境に最適な対策を見つけてください。 シートシャッター 工場の出入口や荷捌き場の防虫対策には、【シートシャッター】が非常に有効です。 シートシャッターの開閉に必要な時間は、わずか3~6秒。 自動かつ高速に開閉するため、従来のシャッターや扉と異なり、虫の侵入を最小限に抑えることができます。 シートシャッターの特長とメリット: 耐久性と防塵・防虫性能 丈夫な素材で構成され、粉塵や虫の侵入を同時に防ぎます。さらに清潔な作業環境を維持します。 省エネ効果 開放時間が短いため空調効率を高め、冷暖房コストの削減にもつながります。 業務効率の向上 フォークリフトや荷物の受け渡し時もスムーズに動作し、作業の妨げになりません。 業務の妨げにならず、防虫性能を向上させるため、シートシャッターは工場にとって欠かせない設備です。 👉 シートシャッター製品はこちら 防虫カーテン 防虫カーテンは、工場の大きな開口部や荷捌き場での防虫対策に非常に有効な設備です。特に導入しやすく、コストパフォーマンスに優れている点で多くの工場に採用されています。 防虫カーテンの特徴とメリット: 虫が嫌がる特殊な素材 防虫カーテンには、虫が認識する光の波長をカットする特殊な素材が使用されています。この素材は虫を寄せ付けないだけでなく、透明度が高いため、作業エリアの視界や自然光を損なうことがありません。また、一部の製品には、虫が嫌がる成分が含まれているため、さらなる防虫効果が期待できます。 さまざまなサイズや形状に対応 開口部の大きさや形状に合わせてオーダーメイドが可能なため、どのようなスペースにも柔軟に対応できます。ストリップ型や一枚物のシート型など、用途や環境に応じて選択肢が豊富です。 通行や作業に支障をきたさない 軽量で柔軟性があるため、人やフォークリフトなどの機器が通行しやすく、業務を妨げません。必要に応じて簡単に開閉できるため、使い勝手も抜群です。 👉 防虫カーテンの製品はこちら ビニール間仕切り 間仕切りは、工場内の広いスペースを効率よく区画し、防虫対策や作業環境の向上を実現するために最適な設備です。 特に屋外環境に近い作業場や、荷捌きスペースでの活用が効果的です。簡易的なクリーンルームのような使い方もできます。 間仕切りの主な特徴とメリット: 広い空間のゾーニング 工場内の大きなエリアを仕切ることで、異なる作業エリアを明確に分けられます。例えば、梱包作業エリアを区切ることで、防虫効果だけでなく作業効率や安全性の向上にもつながります。 隙間を最小限に抑える設計 生地素材を使用した間仕切りは、配管や柱などの障害物にも柔軟に対応可能です。必要な部分に切り込みを入れるだけで、隙間を減らしながら配管や機器を通せるため、従来の金属板よりも高い防虫効果が得られます。 視界や明るさを確保 塩ビなどの透明素材を使用すれば、作業場全体の視認性や自然光を保ちながら、防虫効果を発揮できます。透明度の高い素材は、安全確認が必要な工場作業にも適しています。 👉 ビニール間仕切りの製品はこちら エアカーテン エアカーテンは、開口部に薄くて強力な空気の流れを作り出す送風機を設置し、風の力で虫の侵入を防ぐ設備です。出入り口を常時オープンにしていても、防虫対策が可能です。 エアカーテンの主な特徴とメリット: 業務効率を損なわない防虫対策 扉を閉める必要がなく、人やフォークリフトの通行がスムーズに行えます。 省エネ効果 外部からの温度差を遮断し、空調効率がアップします。 小型の虫には効果的ですが、大型の虫や強い外風には弱いため、シートシャッターや防虫カーテンとの併用がおすすめです。 例えば上述のシートシャッターが開いたときにエアカーテンが起動するように連動させると、お互いの弱点を補完できるでしょう。 また、動作時の騒音問題があるため、作業環境や近隣住民への配慮が必要です。 網戸と排気口ネット 網戸 窓を使った換気を行っている工場では、網戸の点検が重要です。経年劣化による穴や隙間は、虫の侵入を許す原因に。定期的なチェックと必要に応じた交換を行いましょう。 排気口ネット 換気扇や排気口も注意が必要なポイントです。「隙間」を防ぐことが虫対策の基本。専用のネットを取り付けることで、虫の侵入を効果的に防げます。 捕虫器 侵入してしまった虫への対策として、捕虫器も有効です。ただし、設置場所を間違えると逆効果になる場合もあります。 工場内で使用する際は、次の点に注意してください: 青い光が外に漏れない設置場所を選定 外部への誘引を防ぐ工夫 防虫対策は「スキマ」を無くすことが鍵 工場における防虫対策は、どれだけ「スキマ」を無くせるかがポイントです。 弊社では、防虫カーテン、シートシャッター、生地を利用した間仕切りなど、導入しやすい防虫設備を幅広く取り揃えております。まずはお気軽にご相談ください。 👉お問い合わせはこちらから -
2020.05.22
コラム
屋外用カーテン、芯材カーテン、スライドカーテンの選び方
テントやビニール素材を使ったカーテンには取り付け場所、用途により複数の選択肢があります。 今回はその中でも取り付け頻度の多い3種類の選び方をご説明したいと思います。 結論から書くと風のある環境で使わないのであればカーテン、強風、台風に耐えたいのであれば 芯材入りカーテン、高さがあり強度が必要であればスライドカーテンをおすすめいたします。 下記にその理由を説明いたします。 強度 スライドカーテン>芯材入りカーテン>カーテン コスト スライドカーテン>芯材入りカーテン>カーテン 使いやすさ カーテン≧芯材入りカーテン≧スライドカーテン 高さのあるカーテンの操作性 スライドカーテン>芯材入りカーテン≧カーテン 選ぶ条件としては強度、コスト、使いやすさ、ひょっとすると取り付ける下地の条件も在るかもしれません。強度については台風や強風にも耐えなければならない条件であれば、 スライドカーテンか芯材入りカーテンを選ばなくてはいけません。カーテンでは風に抵抗するすべがないため、確実に破損します。 コストについては部材が一番多いスライドカーテンがもちろん一番高く、シンプルなカーテンは安くなります。 使いやすさについては、不等号で表しています。芯材カーテン、スライドカーテンは風に抵抗するために地面と芯材パイプを何かしら固定する必要があり、 通常落としピン(フランス落し)を使用します。つまり落としピンを芯材の本数落としていく、もしくは上げていく作業が必要となります。 それでも芯材カーテンであれば、通りたい幅に応じて数本落としピンを操作を行えば出入りが可能ですが、スライドカーテンに至っては、その性質上一体となった スライドカーテン部分のすべてのピンを操作する必要があり、手間がかかります。その他の方法としてレールを地面に埋め込み、ガイドピンを芯材から延長することで 風への対策を施すこともできます。この方法ですと落としピンをすべて操作する必要がなく使い勝手が大変良くなりますが、レールの埋め込み費用と開口が一時使えなくなることから 選ばれることはまれです。(この方法があるため使いやすさはイコール付きの不等号となっています) 高さの在るカーテン(4mまで)についてはカーテン端部に芯材パイプ(先導パイプ)を取り付けたカーテンが必須となります。操作用のロープで代用することもできますが、 芯材パイプを取り付けることにより上部まで力が伝わり、カーテンが動作しやすく閉じたときに隙間なく占めることもできます。4m以上となると、スライドカーテンのように 面としての機能をもたせた操作性が必要となります。芯材カーテンでは力が伝わりにくく動作がしづらい開口となってしまいます。 ビニールカーテン:シンプルな構造で基本的に地面との取り合いをしません。多少の風に対応するため、地面に打ち込んだグランドフックとカーテンをチェーン等でつなぐこともできますが、 強い風には耐えることができず、不意の強風により破損の原因となります。操作性と機密性を向上させるため、先導にだけマグネット付きの先導入りのパイプを取り付ける場合があります。 ビニールカーテンの欠点である不安定さが解消されるため、おすすめの仕様です。(ただし風には耐えられません) 芯材カーテン:耐風のため芯材のパイプが組み込まれており、強風や台風であっても十分に持ちこたえることができます。(建屋が破損するような強風は別となります)カーテンレールは通常のものよりも大型のアルミレールを使用するか、ハンガードア用の高強度のものを使用します。地面に落とし受けを埋め込み、そちらに落としピンを固定することで風に対して抵抗をします。芯材同士がシートでしか連結されていないため、互いがフリーに動くことができるため、ピンを必要箇所だけ外すことで開きを調整できます。高さは4m程度が目安となります。それ以上となりますと操作が難しくなるとともに、強度を保つために芯材のサイズが大きくなっていきます。風に耐えうる構造としては、最低限芯材カーテンの取り付けをおすすめしております。 スライドカーテン:芯材同士をバツの字にスライドバーでつないだジャバラ構造となっており、カーテンを縮めたときにはスライドバーも幅が縮み芯材カーテン同程度のタタミシロでまとめることができます。ジャバラ構造を取ることで高さの在るカーテンでも力の伝達がしやすくなり、開け閉めが同様となります。弊社のジャバラ仕様はすべてスライドバーにベアリングが組み込まれているため、少ない力で動かすことができます。すべての芯材をつなぐため、カーテンがより面として力を受けることになるため、強度も有利です。ただし、芯材がすべて連結されており、すべての芯材間が等しい間隔で動くため、例えば1mの開口を作るためにもすべての落としピンを抜かなければならない欠点があります。常に締めた状態、開けた状態を保たれるなら問題有りませんが、頻繁な開閉には向いていない仕様となります。 以上一長一短ある仕様ではありますが、その一短を部材、工法を工夫することにより対処することもできます。風向きや開閉頻度等を踏まえご提案できますので、お気軽にお問い合わせください。 タカダ創美の屋外カーテンに関するページはこちらから タカダ創美のビニールカーテンに関するページはこちらから
CATEGORY
選択してください
ARCHIVE
選択してください
- 2025年12月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年8月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (4)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (3)